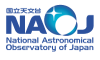| SCI(サイ) | > | 第1回 自然科学研究機構シンポジウム 見えてきた! 宇宙の謎。生命の謎。脳の謎。 |
> | シンポジウム準備ページ > シンポジウムのコンセプト |
シンポジウムのコンセプト
ページ先頭へ↑研究への情熱
はじめに、このシンポジウムをコーディネートした者として、このシンポジウムの狙いがどこにあるのか、どういう考えの下にこのプログラムを組んだのかを明らかにしておきたい。
このシンポジウムの狙いは、
「見えてきた!宇宙の謎。生命の謎。脳の謎。―科学者が語る科学最前線―」
というタイトルに全部含まれている。
このシンポジウムを主催する自然科学研究機構は、日本のサイエンスを代表する五つの研究機関―国立天文台、核融合科学研究所、基礎生物学研究所、生理学研究所、分子科学研究所―の集合体である。
それらの研究所で研究をいま現に行っている、世界でもトップレベルの研究者たちが、次々に舞台の上に登場して自らの研究を語り、その成果をアピールするとともに、自分たちの研究にかける思いを語っていく。
先端科学の研究現場と一般大衆との間には、知識と理解能力の両面で埋められない大きな溝があると思われがちだが、決してそうではない。
先端科学を現場で担っている研究者たちはみんな強い情熱に突き動かされて日夜、研究に勤しんでいる。
「もっとしりたい。」「この謎をどうしても解きたい。」という思いに駆られて、自分の持てる知的エネルギーと肉体的エネルギーを総動員し、かつ精神を研ぎ澄ましながら、常人には理解しがたいことに情熱をとことん傾ける日々を送ってイキるのがサイエンスの研究者たちである。
しかし、そのような頭の中は別世界に住む研究者たちも、その情的世界においては、面白ければ笑い悲しければ涙する、フツーの生身の人間である。そして、そのような情念部分が研究者を研究に駆り立てるドライビング・フォースになっている。たしかに、やっているのは難解なことだが、彼らが、自分の肉声を持って、熱をこめて、自分の情念部分を語るのなら、理屈の部分は必ずしも伝わらなくても、その情熱は伝わるはずだ。
シンポジウムの力点
このシンポジウムの第一の力点は、この「科学者自身が語る」ことによって、科学の最前線で戦い続ける研究者たちの思いを伝えるというところに置かれている。プロの解説者、あるいはプロの語り手に語ってもらうのではなく、不器用でも下手くそでもいいから研究者自身が自分の研究を熱を持って伝えようということである。
もう一つの力点は、この「科学の最前線」というところにある。科学の最前線でやっていることは、相当、難しいことである。そう簡単には説明できない。だから、一般のメディアが科学番組を作るときでも、大衆向けの場合、最前線まで行かずに、一歩も二歩も引いたところで、相当丸めた説明で終ってしまうということがよくある。本当の最前線に行こうとすると、「それじゃ視聴者にわからないよ」のプロデューサーの一言で、強引にわかりやすいヴァージョンに変更を求められるということがよくある。
しかし、サイエンスの取材でいちばん面白いのは、やっぱり本当の最前線なのである。本当の最前線には本当の驚きがあるからである。
しかし、本当の最前線まで行ってしまうと、そこで行われていることがよくわからないということが起こる。その面白さを大衆に伝えることの難しさというのは確かにある。
Imaging Scienceの最先端
今回のシンポジウムの企画でいちばん苦労したのもそこのところである。最前線まで行きたい。しかし、最前線の難しさをどう克服するか。そこで考え出したのが、もっぱらイメージングを駆使して、難しいことも目で見てわからせてしまうという戦略である。それが後半のパネルディスカッション「21世紀はイメージングサイエンスの時代」になった。このパネル部分は、実は、昨年8月、自然科学研究機構の内部で行われた、"Imaging Science"というシンポジウムを基にしている。
このシンポジウムは、自然科学研究機構の「連携研究プロジェクト」として行われた独特のシンポジウムで、機構の内外から264名の参加者(外部参加者36名、内部参加者148名)を集めて、2日間にわたって開かれたものである。
シンポジウムの趣旨は、いまサイエンスの世界で、イメージング(画像、画像技術、画像認識)が、領域を超えて、新しい科学の方法論として、飛躍的に発展を遂げつつあるが、その関係者が一堂に会して意見を交換したら面白いだろう(技術、知識、アイデアの交換ができる)というものだった。
サイエンスの各分野で利用されているイメージング技術は、それぞれに独特だから(例えば、望遠鏡と顕微鏡)必ずしも知識の交換がすぐ役に立つものではないかもしれないが、話し合ってみたら、実は意外な共通点があるのではないか、ということだった。
実際、話し合ってみると、分野を超えて意外な共通性がいろいろ発見されて、テクニカルにお互いに役立つ知識を交換できただけでなく、イメージングそのものを科学する「イメージング・サイエンス」という新しいサイエンスが生まれるのではないか、そういうものを作ろうではないか、というところまで話が進むという画期的なシンポジウムになった。
本日のパネルの演者5名(脳の河西教授を含む)はその八月のシンポジウムでの発表者でもある(基礎生物学研究所の田中実助教授は今回初登場)。
自然科学研究機構とは?
このシンポジウムの背景となった「連携研究プロジェクト」とは何なのかをここで説明しておこう。
先に述べたように、自然科学研究機構は、五つの研究所の集合体だが、この五つの研究所、あまりにも性格が違う、何しろ、研究のフィールドが、宇宙からバイオまで、核融合から脳までと違いすぎるほど違う。ひとつの組織になったものの研究者同士の間は疎遠だった。何かの機会に偶然出会って、お互いに何を言っているのか説明しあっても、相手の言うことがチンプンカンプンで、まるでコミュニケーションが成り立たなかったという嘘のような本当の話もある。
しかし、このままでは、せっかくひとつの組織になった意味がない(事務の合理化などのメリットはあった)、何とか研究の上でも、性格の違う研究組織が一つになったシナジー効果を出そうということで考えられたのが、「連携研究プロジェクト」だったのである。
次に、そもそもなぜ、それほど正確が違う組織が一緒になったのかという点について述べておく。
一言でいうと、それは小泉改革のためなのである。
小泉改革のスローガンは、良く知られているように、「小さな政府」と「民でできることは民に」である。
平成十六年、小泉改革の一環として、国立大学の独立行政法人化がなされた。それとともに、国立研究所もまた独立行政法人化されることになった。日本にはたくさんの国立の研究所(理学系、工学系、文科系、社会科学系などいろいろ)があって、それが学術的研究活動の中核を担ってきた。国立研究所の研究者は当然公務員だったが、それを非公務員型の独立行政法人にすれば、公務員をバサっと減らせるということで、小泉改革の目的(「小さな政府」)に合うということになったのだ。
国立研究所をどのような形の独立行政法人にするかについては、甲論乙論いろいろあったが、結局、規模、研究目的、研究手段、研究拠点、監督官庁などの視点を総合勘案して、いくつかの研究所をクラスター化して、その上にアンブレラ的統合組織を設けるということになった。
その中で、基礎科学としてピュアな自然科学研究を目的として、研究水準も極めて高い、前記五つの研究所が結合してできたのが自然科学研究機構なのである。
このような基礎科学系の研究機構としては、他に、高エネルギー加速器研究機構、情報・システム研究機構などがある。これらはいずれも旧文部省系の国立研究所だった。これらの研究所は、大学が単独ではもてない巨大設備をもって、各大学がそれを共同で利用できるようにした、「大学共同利用機関」にもなっていた。今でもその教育と研究にかかわる費用の基本的性格は変わらないから、大部分は、文科省から運営交付金という形で交付されている。
では、国立研究所時代とどこが違うかといえば、国立研究所時代は、一から十まで、ハシの上げおろしにいたるまで、文科省(と財務省)の強いコントロールがあった。予算を組む時点で、その支出内容はことこまかに決められており、その枠を踏み外すことはいっさい許されなかった。しかし今度は、予算の使い方などにも、一定限度自主的決定権(それは同時に、できるだけ倹約するということが求められるということでもある)が認められるようになったことである。また収入面では、上から支給される運営交付金以外に、自力で稼ぐことも求められるようになった。要するに、収支両面で経営の努力を することが求められるようになったということである。
そのために作られたのが、経営協議会なる組織である。そこに、内部委員として各研究所の所長クラス、外部委員として、大学の学長などの学識経験者ならびに民間の経済人などを入れて、経営的側面を色々論じてもらおうということになった。
その経営協議会なるものが発足するにあたって、その委員の一人になってくれないかと私のところに依頼が来た。私は、「いいですよ」といとも気軽に引き受けた。それというのも、私は自然科学研究機構に結集した五つの研究所を五つともよく知っていたからである。
自然科学研究機構は、あまりにも性格のちがう研究所の寄り合い所帯だったから、一般にはその存在意義がよく分からない組織といわれた。なにしろ、生理学、生物学に、分子科学、それに天文学と核融合研究では、あまりに性格がちがいすぎた。なぜそれがいっしょになるのか、わからないといえば、わからない組織だった。自然科学研究機構に属することになった各研究所の内部の研究者たちにしても、なぜ自分たちが、そのような巨大組織の一部分にならなければならないのか、さっぱりわからなかったろう。
ところが私は、サイエンス・ジャーナリズムの仕事をかれこれ二十年間以上つづけてくる中で、これら研究所のすべてを知っていた。天文台は四回以上取材に行っている。生理研は三回以上、基礎生物研も、核融合研も二回以上取材に行っている。分子研は取材にこそ行かなかったものの、大きな一般向け公開シンポジウムに招かれて話をしにいっている。
民営化の是非
こういう経験を持つ人間として、私はこれら五つの研究所が集まってひとつの大きな機構を作るという話をニュースとして聞いたとき、「オッ、それはいいじゃないか。」とすぐさま思った。五つの研究所とも、研究所として、超一級品と思っていたからだ。それが、経営協議会のメンバーになってくれと頼まれたとき、すぐに引き受けた理由だ。
しかし、研究所の経営といっても、実はそれほどやることがない。収入のほとんどは、文科省から運営交付金として交付されるのだし、その交付金額は、研究所としていい実績(研究業績)をあげている限り、減らされることはない。また、文科省からの運営交付金以外に収入の道があるかといえば、ゼロとはいわないまでも、ほとんどない。
なにしろ、ほとんど純粋の基礎研究だから、研究成果を売ろうたって、売れるような成果はない。基礎研究というのはそもそもが、空気や水のように、万人が必要とする知的公共財を供給する研究であるから、国家が国家資金を投じて推進すべきものであって、民間の誰かが資本の論理に従って供給してくれと、マーケットまかせにしておいたら、誰も供給しなくなってしまうという性格のもので、本当は小泉改革の対象にならないものである。「民間でできることは民間に」の小泉改革の原理にまかせておいたら、いつの間にか誰もやらなくなって、やがて国家がどんどん裏返していってしまうというたぐいのものである。民間にまかせられない、国家が万人のために推進しなければならない典型的なものといってもよい。
結局、基礎研究を任務とする研究所の経営にとって、いちばん大切なポイントは研究実績をあげつづけて、十分な国家資金を引きだしつづけることにかかっているといってよい。そのために何より重要なことは、研究実績において、その任務を十分に果たしていることを社会に常にアピールしていくことだから、ケチな寄付金集めに精を出すことより、あらゆるチャネルを利用しての広報体制をしっかりすることのほうがはるかに・・・。
ページ先頭へ↑
| SCI(サイ) | > | 第1回 自然科学研究機構シンポジウム 見えてきた! 宇宙の謎。生命の謎。脳の謎。 |
> | シンポジウム準備ページ > シンポジウムのコンセプト |